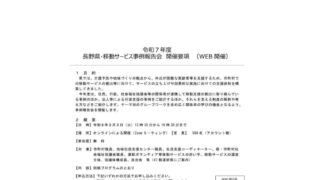 セミナー・シンポジウム等
セミナー・シンポジウム等 長野県移動サービス事例報告会のご案内(2/3WEB開催)
長野県主催「令和7年度移動サービス事例報告会」のご案内(2/3WEB開催)長野県からの委託事業も4年目を終えようとしています。長野県では、介護予防や地域づくりの観点から、外出が困難な高齢者等を支援するため、市町村での移動サービスの創出等に向...
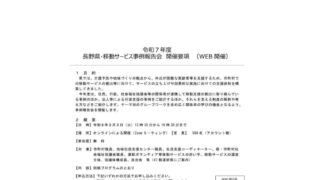 セミナー・シンポジウム等
セミナー・シンポジウム等  研修開催のお知らせ
研修開催のお知らせ  会報(モヴェーレ)
会報(モヴェーレ)  未分類
未分類  政策提言
政策提言  セミナー・シンポジウム等
セミナー・シンポジウム等  調査研究
調査研究  セミナー・シンポジウム等
セミナー・シンポジウム等  書籍等の発行
書籍等の発行 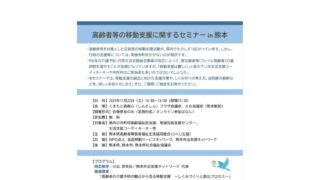 セミナー・シンポジウム等
セミナー・シンポジウム等